W'UP! ★ 7月23日~10月6日 スクワイア家の記憶 -ある英国人技術者の遺品から- 国立歴史民俗博物館 (千葉県佐倉市)

第3展示室 特集展示
スクワイア家の記憶 -ある英国人技術者の遺品から-
Memories of the Squire Family: From the Mementoes of a British Engineer
会 場 国立歴史民俗博物館 総合展示第3展示室特集展示室
開催日 2024年7月23日(火)~10月6日(日)
開館時間
~9月 9:30~17:00(入館は16:30まで)
10月~ 9:30~16:30(入館は16:00まで)
休館日 月曜日(月曜日が休日にあたる場合は開館し、翌日休館※8月13日は開館)、8月6日(火)、9月3日(火)、10月1日(火)
料 金 一般600円(350円)、大学生250円(200円)、高校生以下無料
※()は20名以上の団体料金です。
※総合展示もあわせてご覧になれます。
※障がい者手帳等保持者は手帳等提示により、介助者と共に入館無料です。
※高校生及び大学生の方は、学生証等を提示してください。
※博物館の半券の提示で、当日に限りくらしの植物苑にご入場(16:00まで)できます。また、植物苑の半券の提示で、当日に限り博物館の入館料が割引になります。
公式サイト https://www.rekihaku.ac.jp
お問合せ ハローダイヤル 050-5541-8600
- 宮川春汀 錦絵画帖『有喜世之華』 明治 30~31 年(1897~98) ダラム大学東洋博物館蔵
- 千寿製紙工場全景写真 明治時代 ダラム大学東洋博物館蔵
- 感謝状 明治 37 年(1904) ダラム大学東洋博物館蔵
- マージョリー、ドロシーと森山家の 男の子の写真、森山國蔵写真館で 1902年頃 撮影 ダラム大学東洋博物館蔵
- 林弘之 縮緬本『かちかちやま』 明治 33 年(1900) ダラム大学東洋博物館蔵
- 楊洲周延 錦絵画帖『真美人』 明治 30 年(1897) ダラム大学東洋博物館蔵
明治31年(1898)、イギリス人技術者ジョージ・スクワイア(1868-1930)が日本に招へいされました。日本の近代的製紙業が急速に発展し各地に工場が進出していた時代、ジョージは九州の小倉で操業していた千寿製紙の工場で工場管理一切を任され、小倉と東京の本社間を船で往復しながら、職工の訓練から給与支払いまで細かく目を配り、工場の運営に当たりました。
その後、リディア夫人と二人の幼い娘が合流しました。小倉で暮らしたおよそ3年間、リディア夫人は自宅で娘のマージョリーとドロシーを教育するかたわら、近隣の人たちに英語を教えるなど交流を深めます。
スクワイア夫妻は、小倉の森山國蔵写真館で定期的に姉妹の写真を撮りました。森山家の次男為蔵はリディア夫人から英語を学ぶなど両家は親しく交流し、それはスクワイア家がイギリスに帰国した後も長く続きました。
スクワイア家の日本時代の思い出の品は、1980年前後に姉妹がなくなった後、イギリスのダラム大学に寄贈されました。今回の展示では、20世紀初頭に日本で暮らしたイギリス人技術者一家の遺品を通して、彼らの日本での暮らしを垣間見ます。
なお、この特集展示は歴博と調査研究に関する協力の覚書を結んでいるダラム大学との共同主催事業です。
みどころ
森山國蔵写真館で撮られたスクワイア家の人々の写真を通し、森山家との交流をみる
スクワイア夫妻が娘のために日本で購入した、英語で書かれた昔話などの絵本(縮緬本)や楊洲周延の錦絵画帖『真美人』などの豪華な錦絵揃物を展示
| 住所 | 千葉県佐倉市城内町117 |
| TEL | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |
| WEB | https://www.rekihaku.ac.jp |
| 開館時間 | 3月 ~ 9月 9:30 ~ 17:00、10月 ~ 2月 9:30 ~ 16:30(入館・入苑は閉館の30分前まで) |
| 休み*1 | 月曜日(休日は開館、翌日休館)、年末年始(12月27日〜1月4日)※最新情報はホームページにてご確認ください。 |
| ジャンル*2 | 歴史・考古・民俗関連 |
| 入場料*3 | 一般 600円、大学生 250円、高校生以下無料 ※企画展示の料金はその都度別に定める |
| アクセス*4 | 京成佐倉駅より徒歩約15分、またはバス約5分、またはJR総武本線佐倉駅からバス約15分 |
| 収蔵品 | データベースれきはく https://www.rekihaku.ac.jp/education_research/gallery/database/ |
| *1 このほかに臨時休館あり *2 空欄はオールジャンル *3 イベントにより異なることがあります。高齢者、幼年者、団体割引は要確認 *4 表示時間はあくまでも目安です | |
国立歴史民俗博物館
W'UP!★8月7日~9月8日 「伝統の朝顔」(2024年度) 国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑(千葉県佐倉市)
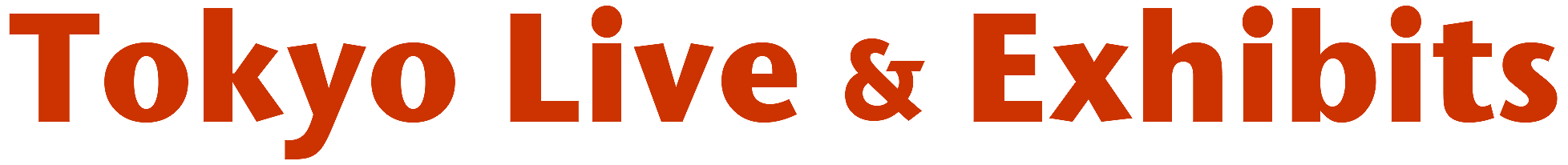








コメント