【The Evangelist of Contemporary Art】Tokyo Gendai 2023: 「東京現代」は何を意味するのだろうか? たしかにアートフェアは、作品(商品)を展示販売する高が見本市である その1
1.グローバルの作法: Tokyo Gendaiを世界と比較する
Tokyo Gendai(以下Tokyo、1)は、東京で待望されていた国際的な現代アートのフェア(見本市+即売会)である。1990年代初めのNICAF(国際コンテンポラリーアートフェア)以来の国際的アートフェアの再登場は、まずはご祝儀相場で他との比較は差し控えたほうがよいのかもしれない。だがフェアのレビューとして、台北で5月に開催された同じ主催者のTaipei Dangdai(以下Taipei、2)と比べるなら、Taipeiに参加しているメガギャラリー(3~14)が不在である。本サイトのレビューで言及したように、Taipeiは欧米のメガやビッグのギャラリーが少ないことで、ヒエラルキーのない解放感にしばし浸れたが、それだけグローバルなマーケットから遠ざかった。Tokyoは、それに輪をかけてグローバルから外れている。
おかげで去年から始まったソウルで開催されるグローバルなアートフェアFrieze Seoulが、Tokyoとは対照的に目立つ結果となった。ここで言うグローバルとは、世界的に活動するメガやビッグなどのギャラリーの多寡で決まるアートフェアのスタンダード(尺度)であり、Frieze Seoulは韓国のマーケットに期待する世界の有力なギャラリーが多数参加したことで、話題を呼んだのである。
Tokyoは、とりあえず海外のギャラリーが出展することで国際的になったが、そのギャラリーで国際的に活動を展開する(世界の主要都市に支店がある)ものが少ないので、グローバルレベルにはない。さらにTaipeiやFrieze Seoulに出展したメガギャラリーがいないことで、TokyoはTaipeiよりローカル色が強まった。ここで言うローカルとは、会場の大半を占めたローカル(日本)のギャラリーのことである。つまるところ参加ギャラリーは国際的になったが、グローバルの体裁は整っていないのが現状である。
実は、グローバルにはもう1つスタンダード(基準)があって、フェアの出展作品に関わるものである。国際的なギャラリーがいくつあったとしても、グローバルなマーケットに流通している作品が揃わなければ、フェアはグローバルではない。では、このグローバルな作品の内容とは何か?
それを知るには、現代アートのマーケットが国際的からグローバルへと位相が変わったことを理解しなければならない。アートフェアなどの国際的イベントは、文字通り多国籍つまり複数の国のアートを集めたイベントであればよい。しかしグローバルなフェアになると、国際的からステージが一段上がり、グローバルなアートの地平が出現する。その上で、グローバルスタンダードに合致する作品が、イベントの多数を占めることが要求される。
その表現の内容が、現代アートのメインストリームの基本条件であるモダンとポストモダンのハイブリッドである。そのためには、アートがモダンとポストモダンをすでに通過していなければならないが、Tokyoの開催地である日本は、1980年代から長期にわたってポストモダンに停滞し、その底なし沼から抜け切れない閉塞状況にある。
もちろん日本でも、モダンやポストモダンの作品がアートフェアに展示されてはいる。その際、それらが現代のハイブリッド作品の前史としてプロットされることはない。そのため日本のアートシーンは、ポストモダンの没歴史的な底なし沼の埋め草として果てしなく作品が繁茂する茫漠とした光景を呈している。
このように、アートの位相が国際的からグローバルに移行して久しいが、その意味でアジアのアートフェアを振り返ると、アジアでは「国安法」(2020年制定)の施行前の香港のArt Basel、2022年ソウルに進出したFriezeを除いて、グローバルなアートフェアはない。Tokyoの姉妹フェアのTaipeiも、グローバルの要件を十分に満たしていない。Taipeiに反映される台北のマーケットより、Tokyoに反映される東京のマーケットは、さらにグローバルから隔たっている。
その代表が、NICAFの末裔のアートフェア東京である。もちろん、ローカルだからといって取引が成立しないことはまったくない。というより、日本も遅ればせながらアートの商品価値に気づき、昨今のアートマーケットは急速に拡大している。だが、作品の商品価値を支える美的価値といえば、心許ない。マーケットに通用する美的価値は、コレクターのかなり偏った個人的趣味しかないというのが、身も蓋もない日本の現状である。しかも、ローカルとグローバルのマーケットの間に深い断絶(日本のマーケット規模は世界の1%と言われているが、作品の単価にして10倍くらいの違い)があり、それを挽回することは容易ではない。
現在ソウルは、Friezeを呼び込むことで、韓国のマーケットをグローバルに接続しようと企図している。それ以外に欧米の有力ギャラリーをソウルに10軒くらい誘致し、着々とグローバル化のレールを敷いている最中である。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
(その2に続く)
(文・写真:市原研太郎)
■今までの市原研太郎執筆のブログ https://tokyo-live-exhibits.com/tag/%e5%b8%82%e5%8e%9f%e7%a0%94%e5%a4%aa%e9%83%8e/
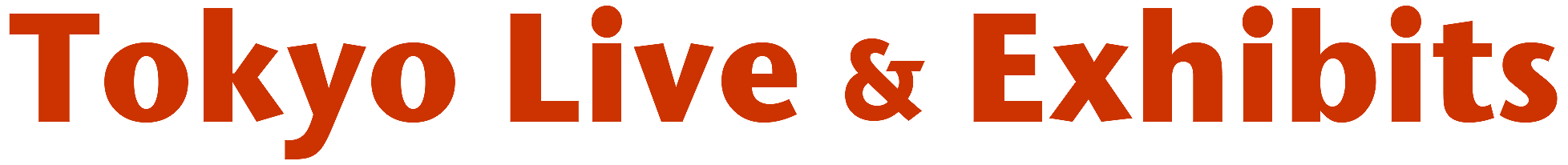













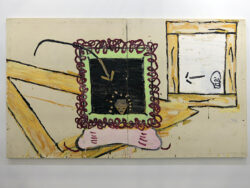


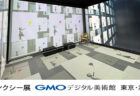
コメント