W'UP!★4月6日~5月12日 Up & Coming 第1回展 展覧会「合図」 Up & Coming(渋谷区神宮前)

2024年4月6日(土)~5月12日(日)
Up & Coming 第1回展 展覧会「合図」
学校法人多摩美術大学は、2024年4月より、卒業後のアーティストキャリア形成支援と、これから躍進しようとしている新しく刺激的な才能と来場者が出会えるオルタナティブ・スペース「Up & Coming」を外苑前にオープン。
Up & Comingとして開催する第1回展は「合図」。物質や文字や空間の諸要素を彫刻家として扱う大石一貴、身の回りで起きた事象を多次元的時空構造と結び付けた絵画やインスタレーションを制作する齋藤春佳、日常生活における些細な感情や違和感からパフォーマンス、映像、テキストなどによってアクションを起こす張小船Boat ZHANGによる3人展です。
また、3月31日(日)には移転プレイベントとして、アーティストの石田尚志、O JUN、栗原一成と文化人類学者の中村寛の4名による「描くこと」をテーマとしたトークイベントを行います。

“ この展覧会を契機に、ここに来る人は作品を見ることになる
━━ 世界に対してスタートの「合図」を送る展覧会 ”
- 展覧会ステイトメントより
Up & Coming 第1回展 展覧会
合図 Signal
アーティスト 大石一貴、齋藤春佳、張小船Boat ZHANG
会 期 2024年4月6日(土)~5月12日(日)
時 間 12:00~19:00(金・土は20:00まで)火曜休場
会 場 Up & Coming(東京都渋谷区神宮前3-42-18)
アクセス 東京メトロ銀座線「外苑前駅」3番出口より徒歩4分、東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」A2出口より徒歩10分、東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5番出口より徒歩13分
URL https://upandcoming.tamabi.ac.jp
※会期中の関連イベントは、上記ウェブサイトにてお知らせします。



展覧会ステイトメント
この度、Up & Comingではこけら落としとしての展覧会「合図」を開催します。
街を歩くからだがそのまま作品を作り、街を歩くからだがそのまま作品を見る。展覧会の会場で、人々はそれぞれが別のコンテキストを持ち寄っている。
Up & Comingの建物は外苑前エリアに位置し、今まで展覧会の会場としては使用されてこなかったスペースです。この展覧会を契機に、ここに来る人は作品を見ることになる。
本展は大石一貴、齋藤春佳、張小船Boat ZHANGの3名の作品によって世界に対してスタートの「合図」を送る展覧会です。
大石一貴は物質や文字や空間の諸要素を彫刻家として扱います。たとえば湿気までもを作品の構成要素とする時、乾ききっていない土の立体が湛える水分とそこに刻まれた詩によって、展示会場からは見えない海岸のイメージが鑑賞者を経由して会場へ流れ込む。その言葉の粒と砂の一粒が重なるのは、個別の物質や出来事が人の知覚を経由して現れているからこそです。それでいて、時にその作品の射程は鑑賞者の目を通過し後方へ遠ざかる宇宙まで達します。
齋藤春佳は身の回りで起きた事象を日常生活では捉えきれない多次元的時空構造と結び付けた絵画やインスタレーションを制作します。その作品経験は鑑賞者と作品の間に生起し、繰り返し再生可能でありつつも過去の自分とすら同じ経験をすることはできないことから、見る行為者の現在地がその都度見つめ返されます。
張小船 Boat ZHANGは日常生活における些細な感情や違和感からパフォーマンス、映像、テキストなどによってアクションを起こします。社会を生きる鑑賞者である私たちは、その逸脱によって脅かされもしますが、その仕草が含むユーモアに導かれて思わず微笑む時、自ずから密かに作品と共犯関係を結びもします。
合言葉、狼煙、サイン、信号、痕跡。
「合図」にはその取り決めを知らない他者には意味がわからないという特徴があります。それでも、作品が放つ「合図」は世界のどこかと結ばれている。
今から100年後のどこか。地球から3光年先のどこか。
あるいは時間や距離では測れないかたちの、どこか。目の前のあなた。
発された「合図」を受け取るもう一方の末端がある。
それぞれ別のコンテキストを持ち寄って会場に辿り着いた人が、作品の放つ「合図」を読み取るための取り決めを手にしていないまま受け取ることになるのはある意味当然で、それでいて、神経細胞が「合図」に向かって手を伸ばしていくうちにその受容器が新たに形作られていくこともある。晴れた朝の見えない花火の音によって今日運動会がどこかで開催されると知ることはできるので、その「合図」の受取手である運動会の主役とは異なる次元で空を眺めるように、ある程度のコンテキストの一致を元に作品と関係を結ぶこともある。作品の放つ「合図」に呼応するのは作者ではなく鑑賞者である可能性もある。展覧会の会場で作品と鑑賞者が出会う。
これからここではいろんなことがある。これまでになかったことがある。
アーティストプロフィール
大石一貴 OISHI Kazuki
1993年山口県生まれ。彫刻家。武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了。 自他の持つ断片的な経験の時空間と、それを知覚させる物理的な事象に着目し、彫刻・インスタレーション・映像・詩などのメディアを横断しながら制作と発表を続けている。
主な個展に「石と文字」秋川河川敷某所(東京・2023年)、「Voyager is with you」Art Center Ongoing(東京・2022年)、「For instance, Humidity」sandwich (CFP)(ブカレスト・2022年)、主なグループ展に、武田龍/大石一貴「HANNAH」 parcel(東京・2024年)、「血は水よりも濃い、何も分かってないのかもしれないから、庭の隅の手作りの洞窟で、くらくけずられた豆腐歯はこなごなにしたたり冷蔵飛び石の形に集まってななめに流れ出すまで」TALION GALLERY(東京・2023年)、
「群馬青年ビエンナーレ2019」群馬県立近代美術館(群馬・2019年)など。
齋藤春佳 SAITO Haruka
1988年長野県生まれ。2011年多摩美術大学美術学部絵画学科油画専攻卒業。「重力や物体の運動エネルギーの総体が便宜的に時間と呼ばれているだけ」という立ち位置から、出来事を時空間の構造と結び付けた絵画、立体、インスタレーション、映像などを制作。
主な展覧会に「レター/アート/プロジェクト『とどく』」渋谷公園通りギャラリー(東京・2022年)、都美セレクショングループ展 2020「描かれたプール、日焼けあとがついた」(日焼け派)東京都美術 館(東京・2020年)、「立ったまま眠る/泳ぎながら喋る」Art Center Ongoing(東京・2020年)、
「飲めないジュースが現実ではないのだとしたら私たちはこの形でこの世界にいないだろう」埼玉県立近代美術館(埼玉・2017年)など。
グループ活動に「日焼け派」、「此処彼処」、「Ongoing Collective」。バンド活動「ほいぽい」。
張小船 Boat ZHANG
1983年中国生まれ。2007年ロンドン大学・ゴールドスミス修了。主に東京と上海を拠点として活動。ストレンジ・ユーモアを持って、個人的な経験や感情をもとに、コンセプチュアル、パフォーマンス、イベント、映像、イメージ、サウンド、テキストなどを自由に扱って、ユニーク且つ普遍的な状況に、即興的に対応しようとしている。
「VOCA展 2022」上野の森美術館(東京・2022年)、「第12回上海ビエンナーレ」上海当代芸術博物館(上海・2018年)など中国、日本、イギリス、キューバで展示している。2021年松本力賞。2019年「Jimei x Arles Discovery Award」ファイナリスト。作品は上海当代芸術博物館、Asia Art Archiveなどに収蔵されている。対馬や室蘭など、日本各地の地域アートプロジェクトにも参加している。
アーティストグループ「row&row」、「・・」、「チームやめよう」のメンバー。たまにはコーヒー代のために文章も書いている。
主な個展に「そうぞう 力 なくなった!? Lonely Consumer」旧横田医院(HOSPITALE PROJECT・鳥取・2023年)、「無断企画展:かえれないわたしたち」Art Center Ongoing(東京・ 2022年)、「iPhoneの葬式」ギャラリートラック(京都市内・2020年)。
アキバタマビ21移転プレイベント:これまでとこれから10
上映+トークイベント「描くこと」
昨年5月から開催してきた「アキバタマビ21移転プレイベント:これまでとこれから」の最終回として、Up & Comingを会場にトークイベントを行います。
作品としての絵画やデザイン、ドローイング、そして鑑賞者が目にする機会の少ない下絵などのスケッチはもちろんのこと、立体や映像、パフォーマンスといったなかでも行われる「描くこと」は、当然ながらアーティストによって一人ひとり表現や手法が異なります。
アキバタマビ21のこれまでとこれからをつなぐ最終回として、制作活動を続ける上で誰もが向き合う、このシンプルな「描くこと」をテーマに取り上げ、それぞれの表現や手法とそれを支える思考について共有します。
今回のイベントでは、登壇者にアーティストの石田尚志、O JUN、栗原一成と文化人類学者の中村寛を迎え、冒頭で「夏の集い 『速玉』」を上映します。この映像は、2020年に行われた石田尚志、O JUN、栗原一成によるパ フォーマンスの記録で、「速玉」とは登壇者4名の活動名です。
上映後のトークではそれぞれの向き合う「描くこと」についてお話しいただきます。
日 時 2024年3月31日(日)18:00~20:00
18:00~「夏の集い 『速玉』」ダイジェスト・ムービー上映
18:40頃~「描くこと」トーク
登壇者 石田尚志、O JUN、栗原一成、中村寛
会場 Up & Coming(東京都渋谷区神宮前3丁目42-18)
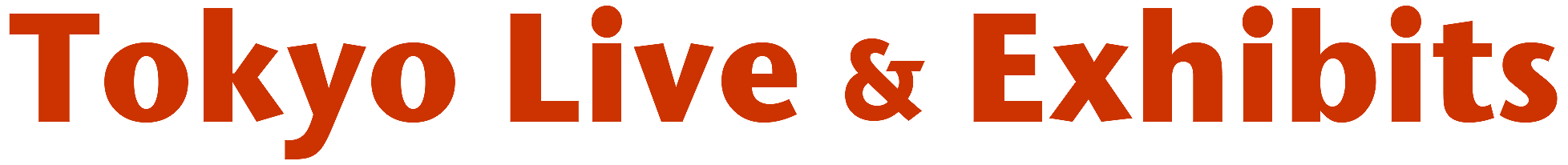


コメント