W'UP★7月3日~8月3日 オートモアイ個展「わたしと地獄をつなぐ透明な糸」 アートかビーフンか白厨(港区六本木)

オートモアイ個展「わたしと地獄をつなぐ透明な糸」
会 場 アートかビーフンか白厨(東京都港区六本木5丁目2−4 朝日生命六本木ビル 2階)
会 期 2024年7月3日(水)~8月3日(土)
(エレベーターの左手奥にある階段を2階までお進みください)
営業時間 17:00~23:00
休業日 日・月
入場料 無料
ホームページ https://artsticker.page.link/AUTOMOAI_paichu
お問合せ 03-6434-9367
アクセス 日比谷線「六本木駅」から徒歩4分、大江戸線「六本木」から徒歩7分、千代田線「乃木坂駅」から徒歩13分、南北線「六本木一丁目駅」から徒歩13分
アートかビーフンか白厨では、2024年7月3日(水)~8月3日(土)の会期で、オートモアイによる「わたしと地獄をつなぐ透明な糸」を開催いたします。
匿名性を帯びた人体、こちらを見返す瞳、言語の外側にいる動物たち、オートモアイの絵画には同じモチーフが繰り返し描かれてきました。それらは記憶の奥底で意味が剥がれ落ちた後に、燐光のように象徴性を帯びて浮かび上がる断片となって不意に目の前に現れます。
「ある日、母親が自作のくまのぬいぐるみを作った。しかしそのぬいぐるみは完成しないまま捨て置かれた。まだ目がつけられていないくまに、私は見つめられていた。」
今回の展示に向けて語られた言葉には、繰り返し描かれるモチーフの隙間から見え隠れしていた”(ほとんど暴力性と重なり合っている)親密さ”、”(論理性から容易く零れ落ちる)実存”としての血縁への関心が色濃く表れています。オートモアイが語る、時間を超越するための装置としての絵画、あるいは展覧会が持ってしまう儀式性に肉薄しようとする細く小さな糸を手繰り寄せると、果たしてどの地獄に繋がっているのでしょうか。
本展示はペインティングに加えて、壁画・ソフトスカルプチャー・ドローイングなどで構成され、オートモアイが長年続けてきた様々な制作を繋ぐ展覧会となっています。また会期中にはトークショーも行われる予定ですので、ぜひ観覧と併せてご参加ください。

オートモアイ AUTO MOAI
2015年からモノクロでの作品の制作を開始、2018年からはカラーも多用し、匿名性の高い“存在”が画面に佇んでいるような 作風で知られる。極めて客観的でもありながら、とてもパーソナルな情景にも見えてくるその作風は、人間同士の関係性や、作品と鑑賞者の関係性など、必要な情報が削ぎ落とされているからこそ見えてくる景色と情景を提示。
2024 “Soul as a butterfly, or the soul of a butterfly” (SORTone Fukuoka、福岡)
2024 Solo Exhibition (OVERGROUND、福岡)
2023 "ボリビアから来たトルコの石" "Turquoise from Bolivia" (PARCO MUSEUM TOKYO、東京)
2022“I wanna meet once again if like that dream” (SAI、東京)
2022 “名前を忘れることで距離をとっていた” (TAV GALLERY、東京)
2022"澱を泳ぐ"(デカメロン、東京)
2021 “Three Different Minds” 3 person exhibition with Nick Atkins, Aki Yamamoto and AUTO MOAI.(MUCCIACCIA GALLERY、London)
2021 "dog,ghost" two-person exhibition with Nick Atkins and AUTO MOAI.(CALM & PUNK GALLEY、東京)
2021 "6 Paintings From 6 Artists"(Parcel、東京)
2021 "Big Ass Beyond Mountains"(Gallery Ascend、香港)
2021 "あやまった世界で愛を語るには"(イセタン・ザ・スペース、東京)
2020 "Buoy" (CALM & PUNK GALLEY、東京)
2019 "ANGEL"(GALLERY X BY PARCO、東京)
2019 "Anonymous"(藤井大丸、京都)
2019 "Permanent Boredom"(TAV GALLERY、東京)
2018 "Endless Beginning"(OVER THE BORDER、東京)
Instagram @auto_moai
X(旧twitter) @auto_moai
W'UP★5月24日~6月23日 「脳はダマせても⇄身体はダマせない♯01」 Gallery & Restaurant 舞台裏(港区虎ノ門)
W'UP★4月20日~5月12日 会田寅次郎「yume tensei」 上野下スタジオ(台東区上野)
会場 GALLERYについて アートかビーフンか⽩厨とは
ArtStickerを運営するTheChainMuseumがプロデュースする飲⾷&アートギャラリーです。再開発で取り壊しの決まっている雑居ビルにて毎⽉プロジェクトを企画します。
Instagramアカウント https://www.instagram.com/paichu_roppongi/
ギャラリーページ https://artsticker.app/paichu
ArtSticker(アートスティッカー)について
株式会社TheChainMuseumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「⼀連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注⽬の若⼿アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。
ArtStickerWebサイト http://bit.ly/3ZeK8vS
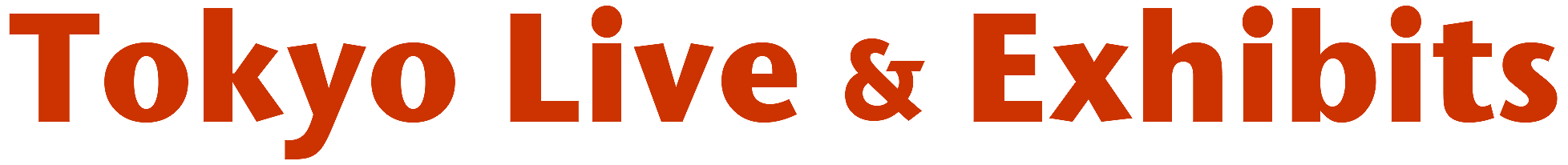



コメント