W'UP! ★5月27日~7月26日 アート・アーカイヴ資料展XXVI 飯田善國-時間の風景 慶應義塾大学アート・センター(港区三田)

アート・アーカイヴ資料展XXVI 飯田善國-時間の風景
会 期 2024年5月27日(月)~7月26日(金)
休館日 土・日・祝日
開館時間 11:00~18:00
会 場 慶應義塾大学アート・センター(東京都港区三田 2-15-45 三田キャンパス南別館1階アート・スペース)
入 場 無料
アクセス 田町駅(JR山手線/JR京浜東北線)徒歩8分、三田駅(都営地下鉄浅草線/都営地下鉄三田線)徒歩7分、赤羽橋駅(都営地下鉄大江戸線)徒歩8分
主 催 慶應義塾大学アート・センター
WEB http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/artarchive26/
※ 最新情報は上記、展覧会ウェブサイトをご確認ください。

彫刻家の飯田善國(1923-2006)は、色とりどりのロープとステンレスを組み合わせた立体作品や、周囲の風景を映しながら動くステンレスのモニュメンタルな作品で知られる彫刻家です。
彼は、はじめ画家としてキャリアをスタートさせましたが、1956年に渡欧した際、ローマで彫刻家のペリクレ・ファッツィーニ(1913-1987)に師事したことなどをきっかけに、彫刻家の道を歩むことになります。飯田はその後ウィーンとベルリンを中心に活動し、木や石を素材とした彫刻を発表しています。
1967年、日本に帰国した飯田は、それに前後して自らの制作における中心的な素材として金属を選択し、ステンレス・スチールの鏡面を巧みに利用した作品を作るようになりました。そこには風の力によって動く彫刻というような、当時の先端的な発想も取り入れられ、また色彩をもったロープなどをステンレスの立体に組み合わせることで、独自の世界を生み出すことになります。
本展では所管するアーカイヴの中から、飯田がプロデューサーとして腕を振るった1969年の「国際鉄鋼彫刻シンポジウム」に関する資料を展示します。このシンポジウムでは招聘された各国の芸術家が、鉄工所の協力を得ながら現代を象徴する素材である鉄を用いた作品を制作しました。これらの作品は、文明の最先端を示すと同時にそれに対する批判も含むという意義を有するだけでなく、翌年1/4に大阪で開催された万国博覧会の会場に設置されたという意味においても、戦後現代美術の展開に大きな足跡を残しました。本展では、当時の飯田や他の芸術家の様子を、写真を中心に振り返ります。
また、飯田が鉄鋼シンポジウムに際して制作した《時間の風景》――本展のタイトルもそこから取られています――のような、飯田自身が「ミラー・モビール」と名付けた鏡面ステンレスによる「動く彫刻」作品はその後日本の各地に設置されており、慶應義塾大学三田キャンパスにも《知識の花弁》(1981)や《星への信号》(1984)といった作品が残されています。時代の異なる作品が見せる時間の流れが、飯田が学生時代を過ごしたキャンパスの経た時間と輻輳的に重なり合うことで生まれる新たな風景の中で、飯田善國に出会っていただけたら幸いです。
関連イベント
講演会
日 時 2024年6月29日(土)15:00より
登壇者 横田 茂(YOKOTA TOKYO取締役/特定非営利活動法人 Japan Cultural Research Institute理事長)、前田 富士男(慶應義塾大学名誉教授)
会 場 慶應義塾大学アート・センター
ギャラリートーク
会期中にギャラリートークを開催予定です。詳細が決定次第ウェブサイトに掲載いたします。
※ 予定は予告なく変更されることがあります。
※ 詳細は展覧会ウェブサイトで順次公開いたします。
http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/artarchive26/
W'UP! ★5月27日~7月26日 アート・アーカイヴ資料展XXVI 飯田善國-時間の風景 慶應義塾大学アート・センター(港区三田)
W'UP! ★6月18日~8月31日 福澤諭吉記念慶應義塾史展示館 2024 年度春季企画展 『慶應義塾と戦争――モノから人へ――』 慶應義塾史展示館企画展示室(港区三田)
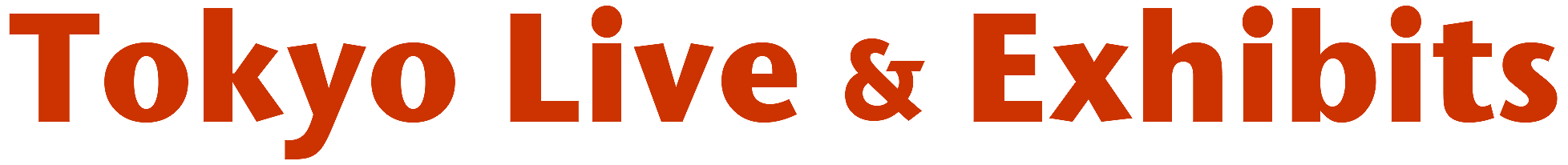


コメント