W'UP! ★7月20日~9月23日 企画展「レイクサイドスペシフィック!—夏休みの美術館観察」 市原湖畔美術館(千葉県市原市)

企画展「レイクサイドスペシフィック!—夏休みの美術館観察」
会 場 市原湖畔美術館
開催日 2024年7月20日(土)~9月23日(月・祝)
開館時間 平日 10:00 ~ 17:00 土曜・祝前日 9:30 ~ 19:00 日曜・祝日 9:30 ~ 18:00
※最終入館は閉館時間 30 分前まで
休館日 月曜日(祝日の場合は翌平日)
入場料 一般 1,000( 800 )円、大高生・65歳以上 800(600)円
※()内は 20 名以上の団体料金。
※中学生以下無料・障害者手帳をお持ちの方(または障害者手帳アプリ「ミライロ ID 」提示)とその介添者(1名)は無料
ホームページ https://lsm-ichihara.jp/
お問合せ 市原湖畔美術館 TEL 0436-98-1525
後 援 市原市教育委員会
- 森洋樹《 lake side 》2019 年 楠、アクリルグアッシュ
- New content for an exhibition, 2024 ⒸMasumi Ishida
- 光岡幸一《ここ》2022 年 Ⓒ Tomoya Iwata(参考図版)
- トモトシ《停滞のトレーニング》2021年 Ⓒ YAKUSHI Kunihiro(参考図版)
- 作品のためのプランドローイング 2024 年Ⓒ BIEN(参考図版)
- 左:「市原市水と彫刻の丘」竣工写真( 1995 年撮影) Ⓒ市原湖畔美術館 右:「市原湖畔美術館」( 2013 年撮影) Ⓒ Tadashi Endo
展覧会の見どころ
➊ 美術館までの風景が彫刻に?
緩やかな弧を描く展示室に添うように建ち並ぶのは、森洋樹による木彫作品です。美術館までの道のりで目にした、山、森、川、湖、ダム、ビル、家などの自然物や人工物をモチーフに、一本の木を彫り出しながら「色」と「線」のみで風景を表現していきます。学部時代は建築を学び、大学院から彫刻専攻に転向した経歴を持つ森の風景の捉え方が色濃く表れた作品群は、私たちがいつも見ているものは何か、考えるきっかけを与えてくれることでしょう。
❷ 美術館にふりそそぐ光
石田真澄は、時間の経過とともに刻々と変わる美術館や周辺環境の表情を “光を見つける” ことを通して発見していきます。本展のために撮り下ろされた新作のみで構成されるインスタレーションは、作家自身の視点を追体験させるような仕草で、自然光が差し込む展示室、屋上広場、外壁に展示されます。中学生の頃から独学で写真を始め、近年は「GINZA」や「POPEYE」などの雑誌、広告、写真集などで注目を集める石田にとって、美術館での発表は本展が初めての機会となります。
❸ 美術館に “新たな導線”
光岡幸一は、建物にテープで文字を書く手法を用いて、美術館に “新たな導線” を作り、美術館で過ごす人々の認識や動きを少しずつ変えていきます。文字で表現されるのは「そこらへん」「あっち」「こっち」「あっちかも」など、正確な順路を示す言葉とは対照的な、曖昧なものばかりです。それらは館内外を散策するように設計され、時にその場に佇ませながら、一見何もないように思えた場所での楽しみ方をささやかに教えてくれることでしょう。
❹ クールな美術館を “ほんわか” させる
本展でトモトシが試みるのは、引越し業者が壁や床に傷がつかないように養生する技術を応用し、美術館建物の鋭角をやわらかく=ほんわかさせていくアクションです。会期中は、他の展示作品と共に、トモトシによる養生が館内各所に現れます。さらに、“ほんわか” させた部分にトモトシが強くぶつかるコミカルな映像作品も展示します。「建築や都市の完璧なデザインはありえない」というトモトシの考えが表れた、会期中のみの刹那的なリノベーションとも言えるでしょう。
❺ リノベーションの痕跡を可視化する
BIENは、約9メートルの吹き抜けに建物の骨組みを現出させ、建物の“形状” や “歴史” の解体/再構築を試みる新作インスタレーションを展開します。かつて、この空間を貫く梁と柱の向こう側は、湖底の世界を表現するための屋外水槽でした。しかし、水中彫刻を設置しようとつくられた水槽は一度も活用されることなく、遺構のように残されていたのです。展示室内に点在するBIENの遊び心ある仕掛けは、リノベーションの痕跡を可視化し、既存の梁と柱をフィクションと現実の境界線に置き換えていきます。
❻ 30年の時を経て明らかになる、美術館の謎
遡ること30年、「水と彫刻の丘」には、とんでもない建築計画が存在していました。地下トンネル、空中デッキ、湖上の回廊……関連展示「学芸員の美術館観察」では、当館の30年余りの資料を掘り起こし明らかにしていくことで時代性を捉え、建築としての当館の魅力に迫ります。また、来館者にも美術館で発見したことを絵やことばで表現していただく「絵日記コーナー」も開設し、美術館を巡りながら、場所を発見していくことの楽しさを共有できる機会をつくります。
会期中のイベント・ワークショップ
会期中は、左官職人さんによる壁塗りのワークショップ、リノベーションを担当した建築ユニット・カワグチテイ建築計画(川口有子+鄭仁愉)をゲストに迎えたトークなど、建物に関連するイベントを開催します。そのほか、出展作家によるイベントも多数開催予定です。
➊ 左官ワークショップ「壁塗り!」申込終了
美術館の地層のような外壁は、1994年、左官職人さんにより表現されたもの。職人さん指導のもと、コテを使った壁塗りに挑戦します。
日時 7/21(日)13:00〜15:00
講師 冨澤政史(左官職人)
定員 20名
参加費 1,000円(別途要入館料)
対象 どなたさまでも
会期中は、左官職人さんによる壁塗りのワークショップ、リノベーションを担当した建築ユニット・カワグチテイ建築計画(川口有子+鄭仁愉)をゲストに迎えたトークなど、建物に関連するイベントを開催します。そのほか、出展作家によるイベントも多数開催予定です。
❷ 建築トーク「リノベーション!」
「水と彫刻の丘」リノベーションコンペ(審査員長:伊東豊雄氏)を勝ち取ったのは、山本理顕設計工場を独立した2人組(当時、有設計室)。このデビュー作で千葉県建築文化賞最優秀賞(2015)、日本建築学会作品選集新人賞(2015)を受賞。当館の建築リノベーションの秘話をたっぷりお話しいただきます。
日時 7/27(土)14:00〜15:30
ゲスト カワグチテイ建築計画(川口有子 + 鄭仁愉)
定員 50名
参加費 1,000 円(別途要入館料)
❸ ナイトマルシェ「ネオレトロナイト!」
毎月第 4 土曜日、当館芝生広場にて開催している「湖畔とピクニックとマルシェ」。7月は15時よりナイトマルシェとして開催予定。古き良き時代を感じさせるレトロ雑貨や昔懐かしい食べ物を楽しむことができます。
日時 7月27日(土)15:00~19:00
入場無料(別途要入館料)
共催 旅する千の風のパレード
❹ ワークショップ「こっぱ!」
出展作家の森洋樹さんと一緒に、彫刻作品を制作するときに出た木のかけら「こっぱ」を組み合わせて風景をつくります。
日時 8/10(土)13:00~15:00
講師 森洋樹(出展作家)
定員 20名
参加費 1,000 円(別途要入館料)
対象 どなたさまでも
❺「アーティストトーク!」
出展作家の石田真澄さんをゲストに迎え、本展に対する思いや出展作の制作背景をお話しいただきます。
日時 8/11(日)13:00〜14:00
ゲスト 石田真澄(出展作家)
定員 50名
参加費 無料(別途要入館料)
出展作家プロフィール
森洋樹 Hiroki Mori(彫刻家)
1988年富山県生まれ。2012年 武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業、2014年 武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程美術専攻彫刻コース修了。日常生活で何気なく思い込んでいる「もの」のイメージをリセットし、自分たちが見ているものは何か意識するきっかけとなる木彫作品を制作している。主な個展に、18 年「 one side 」(銀座蔦屋書店 GINZA ATRIUM、東京)、主なグループ展に、23 年「出張モノローグス #2 」( GASBON METABOLISM、山梨)、同年「 proepi to puroepi 」(コートギャラリー国立、東京)など。
石田真澄 Masumi Ishida(写真家)
1998年埼玉県生まれ。雑誌や広告などで活動。17年5月、自身初の個展「GINGER ALE 」を開催後、18年2月、初作品集「light years - 光年 - 」をTISSUE PAPERS より刊行。19年8月、2冊目の作品集「everything will flow 」、21年、3冊目の作品集「 echo 」を同社より刊行。主な個展に、17年「 GINGER ALE 」(gallery ROCKET、東京)、22 年「 otototoi 」( BOOK AND SONS、東京)、主なグループ展に、19年「LOOKING THROUGH THE WINDOW 」( GYRE GALLERY、東京)など。作品集『echo』2021,カラーネガフィルム(TISSUE PAPERS)
光岡幸一 Koichi Mitsuoka(美術家)
1990年愛知県生まれ。武蔵野美術大学建築学科で学んだ後、2016 年に東京藝術大学大学院油画科修了。「名前は、字がすべて左右対称になる様にと祖父がつけてくれて、読みは母が考えてくれた。(ゆきかずになる可能性もあった。)宇多田ヒカルのPVを作りたいという、ただその一心で美大を目指し、唯一受かった建築科に入学し、いろいろあって今は美術家を名乗っている。矢野顕子が歌うみたいに、ランジャタイが漫才をするみたいに、自分も何かをつくっていきたい。一番最初に縄文土器をつくった人はどんな人だったんだろうか?」
トモトシ tomotosi(映像作家)
1983年山口県生まれ。国立大学法人豊橋技術科学大学建設工学課程を卒業後 10 年にわたって建築設計・都市計画に携わる。2014 年より展覧会での発表を開始。「人の動きを変容させるアクション」をテーマに、主に映像作品を制作している。2020 年より東京でトモ都市美術館を運営し、新しい都市の使い方を提案している。主な展覧会に、19年「あいちトリエンナーレ 2019 」(豊田市)、同年「有酸素ナンパ」(埼玉県立近代美術館、埼玉)、23 年「絶対的遅延計画」(TAV GALLERY、東京)など。
BIEN ビエン(美術家)
1993年東京都生まれ。アニメーション表現や文字、記号などに着目し、その形状や意味を解体 / 再構築する抽象的なドローイングをはじめ、近年では映像、彫刻、インストラクション、インスタレーションなどメディアを横断しながら、事物の表象に問いかける作品を発表。多様なカルチャーの文脈を取り入れたアプローチもまた、BIEN の表現の特徴である。主な個展に、21 年「 DUSKDAWNDUST 」( PARCEL, HARUKAITO by island、東京)、23 年「 PlanetesQue: The Case of B 」( PARCEL、東京)、主なグループ展に、18 年「理由なき反抗」(ワタリウム美術館、東京)、20 年「 PARALLEL ARCHEOLOGY 」( OIL by 美術手帖ギャラリー、東京)など。
【常設展】2023年度 第4回「深沢幸雄の人間劇場」
当館常設展示室では、日本を代表する銅版画家であり、市原市名誉市民である深沢幸雄の作品を主に、市原市にゆかりのある作家の作品を、年に4回の展示替えを行い、紹介しています。
本展は、銅版画家・深沢幸雄の創作人生の集大成ともいえる、「人間」を主題とした晩年の作品を展示いたします。1954年、独学での銅版画制作のスタートから、1962年にメキシコとの出会いでの大きな作風の変化、そこから1980年代に入りまたもや作風の変化が訪れます。仮想空間の中で抽象化された人間がユーモラスな存在として描かれ、技法に関しても、試行錯誤や実験の末に開発してきたあらゆる技法を用いるようになります。1980年代から2000年代の作品21点を展示いたします。
詳細はこちら https://lsm-ichihara.jp/collection/%e6%b7%b1%e6%b2%a2%e5%b9%b8%e9%9b%84%e3%81%ae%e4%ba%ba%e9%96%93%e5%8a%87%e5%a0%b4/
【同時期開催の常設展】市原市コレクション
市原湖畔美術館では2013年のリニューアル以後、常設展示室において、日本を代表する銅版画家であり、市原市名誉市民である深沢幸雄の作品を主に、市原市にゆかりのある作家の作品を、年に4 回の展示替えを行い、紹介しています。
本展では、市原市のコレクションより「みる」をテーマに、深沢幸雄他、胡子修司、河内成幸などの銅版画を中心にこれまであまり公開してこなかった作品も展示。市原市にゆかりのある著名な作家の作品20点をご紹介いたします。
詳細はこちら市原市コレクション 市原湖畔美術館/ICHIHARA LAKESIDE MUSEUM (lsm-ichihara.jp)
| 住所 | 千葉県市原市不入 75-1 |
| TEL | 0436-98-1525 |
| WEB | https://lsm-ichihara.jp/ |
| 開館時間*1 | 平日:10:00~17:00、土曜・祝前日 9:30~19:00 日曜・祝日 9:30~18:00 ※最終入館は閉館時間の30分前まで |
| 休み*2 | 月(休日の場合は翌平日)、(2024年3月23日〜6月23日の期間は火曜休館 ※4月30日を除く)年末年始休館 12/28~1/3 |
| ジャンル*3 | 現代美術 |
| 入場料*4 | 展覧会により異なります |
| アクセス*5 | 小湊鉄道高滝駅より徒歩20分 |
| 収蔵品 | 市原湖畔美術館には、企画展示室の他、常設展示室がある。常設展示室では、年に4回の展示の入れ替えを行い、市原市収蔵作品の中から、銅版画家・深沢幸雄の作品を中心に展示を行っている。※市原湖畔美術館は、約500点の深沢作品を所蔵する国内では有数の美術館です。 |
| *1 展覧会・イベント最終日は早く終了する場合あり *2 このほかに年末年始・臨時休業あり *3 空欄はオールジャンル *4 イベントにより異なることがあります。高齢者、幼年者、団体割引は要確認*5 表示時間はあくまでも目安です | |
市原湖畔美術館

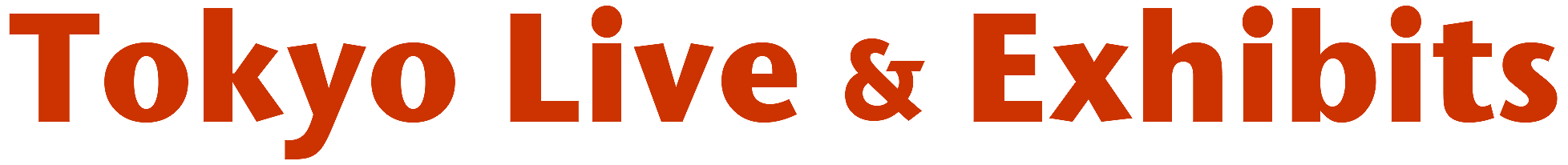







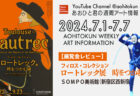
コメント