W'UP!★5月1日~6月28日 「くつろぎの友 お茶」展 OBENTO Gallery(中央区日本橋茅場町)

2024年5月1日(水)~6月28日(金)
「くつろぎの友 お茶」展
日本の弁当文化と食文化の魅力を発信する『OBENTO Gallery』にて「日本のお茶文化」をテーマとした企画展を開催します。
古来、「お茶」は薬として重宝されていました。日本では喫茶の風習は高貴な人々の嗜みとしてまた茶道といわれるひとつの芸能として、独自の発展を遂げていきます。また、「お茶」は戦国大名たちがその地位を示すための手段に利用したり、近代においては日本経済の発展を支えた重要な輸出品目でもありました。今回はこのような歴史の中で育まれたお茶の文化について紹介します。
展示のみどころ
「お茶」を政治利用した戦国大名たち
織田信長は、権力を誇示するため「名物狩り」※1を行い、収集した茶道具で茶会を催しました。また、勲功のあった武将には茶器を与え、茶会を催すことを許可しました。豊臣秀吉においては、関白就任の際に禁中茶会を開いたり、黄金の茶室をつくらせるなど、天下人の権威を示しました。本展では当時の黄金の茶室や大茶会のパネルを展示し、その豪華な様子をご覧いただけます。
※1織田信長によって行われた茶の湯の名物道具の収集
明治の日本経済を支えた「お茶」
明治時代、「お茶」は「生糸」と並ぶ重要な輸出品目でした。 茶産地の開拓や輸出港の整備など政府の援助もあり、最盛期には、当時の輸出総額の15~20%を占めるまでになります。 本展では、輸出用のお茶を製茶する様子がわかるパネルや製品に貼っていたラベルを展示し、当時の様子をご覧いただけます。
会 場 Plenus OBENTO Gallery(東京都中央区日本橋茅場町1丁目7番1号 日本橋弥生ビルディング1F プレナス茅場町オフィス)
会 期 2024年5月1日(水)〜6月28日(金)
開館時間 9:00~17: 30
休館日 土日、祝日
入場料 無料
Plenus OBENTO Galleryホームページ https://www.plenus.co.jp/obentogallery/
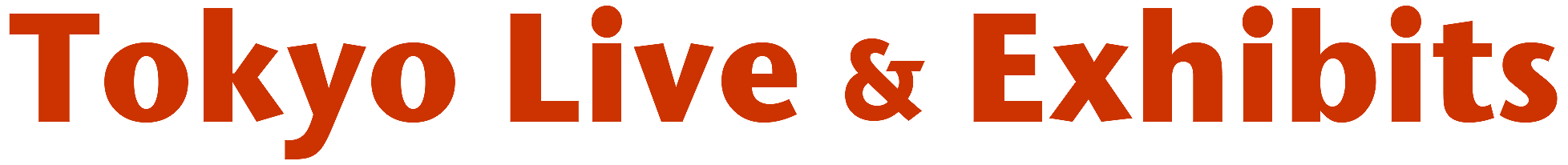




コメント