W'UP!★12月14日~12月22日 未来につながる廃材アートの世界 サステナブルアート作品展 日本橋髙島屋S.C.本館8階特設会場(中央区日本橋)

2023年12月14日(木)~12月22日(金)
未来につながる廃材アートの世界 サステナブルアート作品展
SDGs(Sustainable Development Goals)は、2015年国連サミットで採択された、未来により良い環境を残す「持続可能な社会」を目指すため設けられた17の国際目標で構成されています。現状、ますますその取り組みが必要となるなか、本展では、「サステナブルアート」を代表する作家たちを紹介いたします。
昨今、環境問題をテーマに作品発表するアーティストは少なくありませんが、今回は特に「廃材」を素材として活用する3名のアーティスト―古紙ダンボールのみを使用し生き物の造形美や性質をユニークにとらえた立体作品を制作する玉田多紀氏、ガーナのスラムで暮らす人々の人権と環境問題を改善するため電子ゴミなどの廃棄物で作品を制作する長坂真護氏、廃材を使用し原寸大サイズの動物を制作する加治聖哉氏―にスポットを当てています。彼らの作品はどれも親しみやすく老若男女どなたでも楽しんでいただけるもので、SDGsの理解・取り組みへのきっかけとしていただければ幸いです。
未来につながる廃材アートの世界 サステナブルアート作品展
会 期 2023年12月14日(木)~12月22日(金)
会 場 日本橋高島屋S.C.本館8階特設会場
入場時間 10:30~19:00(19:30閉場) ※最終日は16:00閉場
入場料 無料
企画協力 アート·ベンチャー·オフィス ショウ
出品作家
玉田多紀(TAMADA TAKI)
造形作家
1983年 兵庫県生まれ
2007年 多摩美術大学造形表現学部造形学科卒業
古紙ダンボールのみを使用し生き物の造形美や性質をユニークに捉えた立体作品を制作。
国内外の展覧会、ウインドウディスプレイ、TVメディアやワークショップでも精力的に活動。
ダンボールの強度と柔軟性を生かした独自の技法を美術教育の現場でも広めている。
2023年、平塚市美術館、尼崎市総合文化センターにて「造形作家 玉田多紀 ダンボール物語」を開催。
※展示点数 40点(予定)
Tamada Taki - Official Website http://tamadataki.com

【ワークシヨップ開催】
「古紙ダンボールで作る生き物」
日時 12月16日(土) 1. 10:30〜 2. 14:00〜
※各回15分前から受付開始
参加資格 小学1年生~中学3年生(保護者同伴)
定員 各回15名様(事前予約制、定員になり次第締め切り)
参加費 2,000円
※お申込みは高島屋S.Cホームページ「廃材アートの世界展」ホームぺージにて1か月前から開始予定。
長坂 真護(NAGASAKA MAGO)
MAGO CREATION株式会社代表取締役、美術家
1984年福井県生まれ。
2017年、ガーナのスラム街・アグボグブロシーを訪れ、先進国が捨てた電子機器を燃やすことで生計を立てる人々と出会う。
以降、廃棄物で作品を制作し、その売上から生まれた資金で現地にリサイクル工場建設を進めるほか、環境を汚染しない農業やEVなどの事業を展開。経済・文化・環境(社会貢献)の3軸が好循環する新しい資本主義の仕組み「サステナブル・キャピタリズム」を提唱し、スラム街をサステナブルタウンへ変貌させるため、日々精力的に活動を続けている。
2022年9月、東京「上野の森美術館」にて自身初となる美術館個展を開催。同年11月、第51回ベストドレッサー賞、学術・文化部門受賞。
ガーナに「MAGO MOTORS LTD」を設立し、現在ガーナ人38名が働いている。(2023年8月時点)
※展示点数10点(予定)
長坂真護 オンラインギャラリー MAGO GALLERY https://www.magogallery.online/

加治 聖哉(KAJI SEIYA)
廃材再生師
1996年生まれ。新潟県村上市出身。
2018年長岡造形大学美術工芸学科卒業。
大学在学中より長岡市をはじめ、多くの地域に作品を提供し、地域活動にも積極的に関わる。大学卒業後、有限会社カイカイキキに在籍。
現在は、廃材で原寸大サイズの動物を作るアーティストとして独立して活動。
『役目を終え、死んでしまった「廃材」たちに、もう一度、「生命)」を吹き込む』をコンセプトに「廃材」でダイナミックな等身大の動物から手のひらサイズの動物まで制作。
※展示点数 6点(予定)
廃材再生師 加治聖哉 - Scrap wood artist https://seiyakaji.com

※展示作品は変更になる場合がございます。
お問合せ 日本橋高島屋 03-3211-4111(代表)
W’UP★12月13日〜2024年1月8日 -龍神・龍王- 金子 富之展 日本橋高島屋S.C. 本館6階 美術画廊(中央区日本橋)
日本橋 髙島屋 S.C.(美術画廊、美術画廊X、美術工芸サロン)
W’UP! ★9月16日~2024年2月25日 知られざる陶彫 「陶の仏 ―近代常滑における陶彫」展 髙島屋史料館TOKYO(中央区日本橋)
髙島屋史料館TOKYO(中央区日本橋)
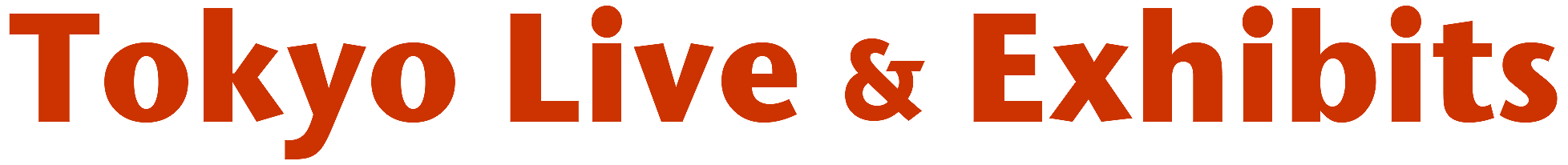


コメント